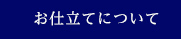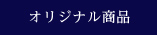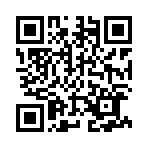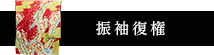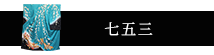2019年04月01日
娘の十三参り
歴史的な発表がなされたこの日に、私たち家族は娘の十三参りを行わせていただきました。
十三参りとは本来、女の子が大人に成長していく過程の節目となる数え年十三の春に、虚空蔵菩薩様にお参りをして智恵と福徳を授かる風習と言われています。
なぜこういった行事が行われるのかは諸説あり、なかでも有力なのは干支がちょうど一周する年なので厄年とも考えられ、厄払いの意味からという説です。そこに菩薩のなかで十三番目に誕生したといわれる虚空蔵菩薩が結びつけられ、虚空蔵様の主な功徳である「智恵」を授かる行事として広まったということです。
もちろん、現代で行う場合には必ずしも虚空蔵菩薩のある寺院を探す必要はなく、地元の氏神様や菩提寺で構わないです。私たちは氏神様である富士山本宮浅間大社にお参りしてきました。

帰ってきてから撮った一枚を載せてみます。十三参りでは本裁ちの着物に肩揚げをして着ることになります。これが終わると肩揚げもはずし、だんだんと大人への階段を登っていくことになるということです。

帯は岡重の染帯。着物も帯も、今の時期だからこそという色を意識して揃えてみました。
お客様の着姿などは、よほど特別な理由がない限りここには載せないということをポリシーとしている当店ですが、こういった行事の一例として参考にしていただければという思いから自分の娘の姿は載せてみました。ただの親バカという面も否定しませんが。
十三参りは古来から、どちらかというと関西地方で盛んな行事であり、こちらの地方では馴染みが薄いという方も多いかもしれません。
しかし、子供の成長を感じるという意味では、七五三よりもある意味で感慨深いものがあるように思います。実際、今日この行事を済ませてきた父親としてそう実感します。
お母様の着物に揚げをして着させてあげれば良いのですし、この時期にしかないお子さまの節目をぜひ祝ってあげてほしいと思いました。

にほんブログ村
十三参りとは本来、女の子が大人に成長していく過程の節目となる数え年十三の春に、虚空蔵菩薩様にお参りをして智恵と福徳を授かる風習と言われています。
なぜこういった行事が行われるのかは諸説あり、なかでも有力なのは干支がちょうど一周する年なので厄年とも考えられ、厄払いの意味からという説です。そこに菩薩のなかで十三番目に誕生したといわれる虚空蔵菩薩が結びつけられ、虚空蔵様の主な功徳である「智恵」を授かる行事として広まったということです。
もちろん、現代で行う場合には必ずしも虚空蔵菩薩のある寺院を探す必要はなく、地元の氏神様や菩提寺で構わないです。私たちは氏神様である富士山本宮浅間大社にお参りしてきました。
帰ってきてから撮った一枚を載せてみます。十三参りでは本裁ちの着物に肩揚げをして着ることになります。これが終わると肩揚げもはずし、だんだんと大人への階段を登っていくことになるということです。
帯は岡重の染帯。着物も帯も、今の時期だからこそという色を意識して揃えてみました。
お客様の着姿などは、よほど特別な理由がない限りここには載せないということをポリシーとしている当店ですが、こういった行事の一例として参考にしていただければという思いから自分の娘の姿は載せてみました。ただの親バカという面も否定しませんが。
十三参りは古来から、どちらかというと関西地方で盛んな行事であり、こちらの地方では馴染みが薄いという方も多いかもしれません。
しかし、子供の成長を感じるという意味では、七五三よりもある意味で感慨深いものがあるように思います。実際、今日この行事を済ませてきた父親としてそう実感します。
お母様の着物に揚げをして着させてあげれば良いのですし、この時期にしかないお子さまの節目をぜひ祝ってあげてほしいと思いました。
にほんブログ村