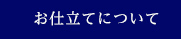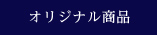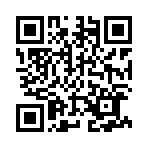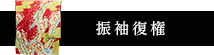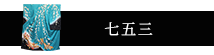2020年02月09日
帯清袋帯 片輪車文様
今日は袋帯を紹介します。

西陣帯清の袋帯。当店では主に振袖に合わせる時に重宝させてもらっています。

技法的には佐賀錦をベースにした独自のもので、従来の佐賀錦では金銀の箔糸を経糸として織り込むのに対し、帯清では経に絹糸を使います。箔糸は緯糸とは別で横に織り込むことで、その独特の風合いを表現しています。この技法は特許を取得してあるそうです。

伝統的文様を選びながら、それを大胆に表現する意匠も特徴のひとつです。本品は片輪車文様。平安時代にお公家さんが使用した牛車の車輪を、乾燥して破損することを防ぐために時々はずして鴨川の流れにつけた姿を文様化したものと言われています。
この文様を見るたびに思うのですが、車輪を川に浸している姿を見て文様化しようと思うセンスってすごいですね。それをまた何百年以上も引き継ぐ私たち日本人は、やはり只者ではないと思うのです。大袈裟でしょうか。
培われた技法も感覚も、しっかり繋いでいきたいものです。本品は当店では振袖に合わせることが多いですが、もちろん訪問着などそれ以降の着物にも心強いパートナーになってくれます。末長く愛用できる帯ですよ。

にほんブログ村
西陣帯清の袋帯。当店では主に振袖に合わせる時に重宝させてもらっています。
技法的には佐賀錦をベースにした独自のもので、従来の佐賀錦では金銀の箔糸を経糸として織り込むのに対し、帯清では経に絹糸を使います。箔糸は緯糸とは別で横に織り込むことで、その独特の風合いを表現しています。この技法は特許を取得してあるそうです。
伝統的文様を選びながら、それを大胆に表現する意匠も特徴のひとつです。本品は片輪車文様。平安時代にお公家さんが使用した牛車の車輪を、乾燥して破損することを防ぐために時々はずして鴨川の流れにつけた姿を文様化したものと言われています。
この文様を見るたびに思うのですが、車輪を川に浸している姿を見て文様化しようと思うセンスってすごいですね。それをまた何百年以上も引き継ぐ私たち日本人は、やはり只者ではないと思うのです。大袈裟でしょうか。
培われた技法も感覚も、しっかり繋いでいきたいものです。本品は当店では振袖に合わせることが多いですが、もちろん訪問着などそれ以降の着物にも心強いパートナーになってくれます。末長く愛用できる帯ですよ。
にほんブログ村
Posted by きものかわむら at 14:36│Comments(0)
│帯